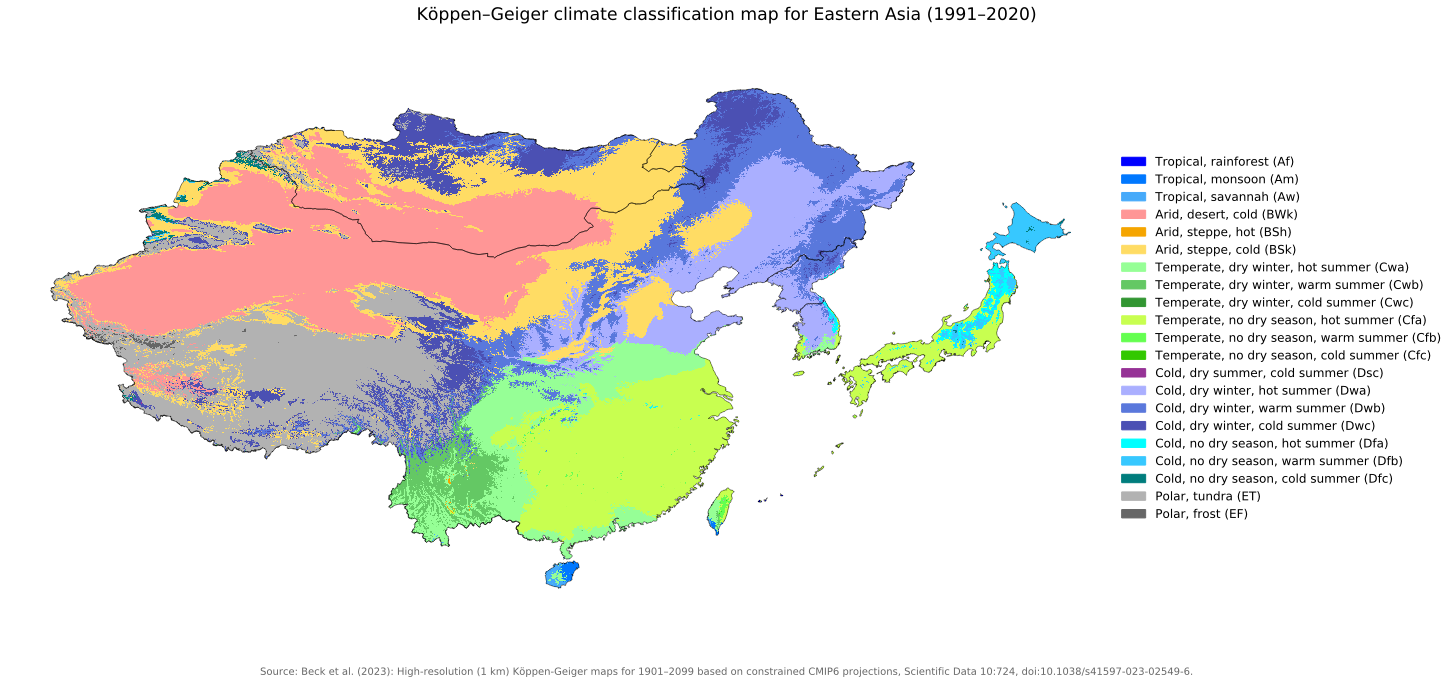東アジアの貿易史|15世紀と18世紀の歴史が特に重要!
東アジアって、今でこそ世界経済にとって欠かせないエリアだけど、過去にも国際貿易の舞台として大きな存在感を放っていた時期があるんです。結論からいえば、15世紀と18世紀は東アジアの貿易のターニングポイントで、世界とのつながり方がガラッと変わった重要な時期 なんです。特に中国・日本・朝鮮の動きがポイントで、外との接点をどう持つか、それぞれの国の判断が世界経済にも影響を与えていたんですね。
|
|
|
|
|
|
15世紀:大航海時代の幕開けと明の鄭和遠征
15世紀といえば、ヨーロッパでいわゆる「大航海時代」が始まるタイミング。でもそのちょっと前、実は中国でも大規模な海洋活動が行われていたんです。
鄭和の大遠征と明の海洋支配
中国の明の時代、1405年から鄭和という宦官が、なんと7回にわたってアジア~東アフリカまでの大航海を実施しました。巨大な船団で100隻以上、数万人規模というスケール。目的は交易だけでなく、「中華が世界の中心である」っていう権威の誇示も含まれてたんですね。
朝貢貿易のシステム
この頃の中国は「朝貢貿易」っていう仕組みを重視していて、外国の使者が中国に贈り物を持ってきて、「あなたたちは我々の臣下です」って形式的に表明。そのお礼に明が豪華な品を返す、っていう形で貿易が成立してたんです。経済というよりも、政治的な関係の中で成り立っていた貿易ですね。
日本と朝鮮の15世紀貿易
日本では勘合貿易ってのが行われてました。これは明と日本が正式な貿易をするために発行した「勘合符」って証明書を使う制度。朝鮮もまた、李氏朝鮮として中国との関係を維持しながら貿易をしていて、特に明との絹や書籍のやりとりが盛んでした。
|
|
|
18世紀:グローバル貿易ネットワークへの組み込み
さて、18世紀になると、世界はすでに「グローバル経済」の入口に差し掛かっていて、ヨーロッパ勢が本格的にアジア市場に進出しはじめます。ここで東アジアの立ち位置が再び問われることになるんです。
清朝と茶・陶磁器の輸出
この時代の清は、茶や陶磁器、絹といった人気商品をヨーロッパへどんどん輸出してました。イギリスやフランスが欲しがるものばっかり。お金の代わりに「銀」で支払われることが多く、中国には大量の銀が流れ込んでいたんですね。
中国の一港開放政策と貿易制限
でも清朝は、「広州」一港だけに貿易を制限する「一港制」をとってました。外国船は広州でしか貿易できないっていうルール。これは西洋側からするとけっこう不満で、「もっと自由に商売させてよ~!」って思ってたわけです。のちのアヘン戦争へつながる不満の種にもなっていました。
鎖国中の日本と出島貿易
この頃の日本はご存知、鎖国中。といっても完全に閉じてたわけじゃなく、長崎の出島を通じてオランダや中国と限定的に貿易してました。特にオランダとは、ヨーロッパからの科学書や医学、工業技術などを入れる「窓口」として機能していて、いわば世界との細いパイプだったんですね。
|
|
|
東アジアの貿易が持つ世界史的意義
ここまで見てきたように、15世紀と18世紀、それぞれの時代に東アジアは世界の流れにどう向き合うかを試されていました。興味深いのは、積極的に海外と関わった15世紀と、選択的に門を閉じていた18世紀で、貿易に対する姿勢がまったく違うことです。
交易=経済活動以上の意味
15世紀の明や日本の貿易は、単にお金儲けじゃなくて「政治的関係づくり」や「国威の発揚」が大きかった。一方で18世紀になると、経済の論理が色濃くなって、東アジアが資源や商品を供給する「世界の一部」として組み込まれていく構図が強まっていきます。
ヨーロッパの海洋進出との対比
ヨーロッパ諸国がこぞって海に出て植民地を拡大していったのに対して、東アジアはむしろ「守る」姿勢が強かった。これは地理的・文化的な要因も大きいですが、それぞれの地域が世界とどう関わるかの選択の違いとして見ると、すごく面白いんです。
15世紀と18世紀の東アジアの貿易は、ただの商取引の話じゃありません。それぞれの時代の国のあり方や世界との向き合い方を映す鏡だったんです。積極的に海に出た時代と、自国を守ろうとした時代。どちらにもその時代ならではの意味があって、今の東アジアの姿にもしっかりつながってるんですよね。
|
|
|