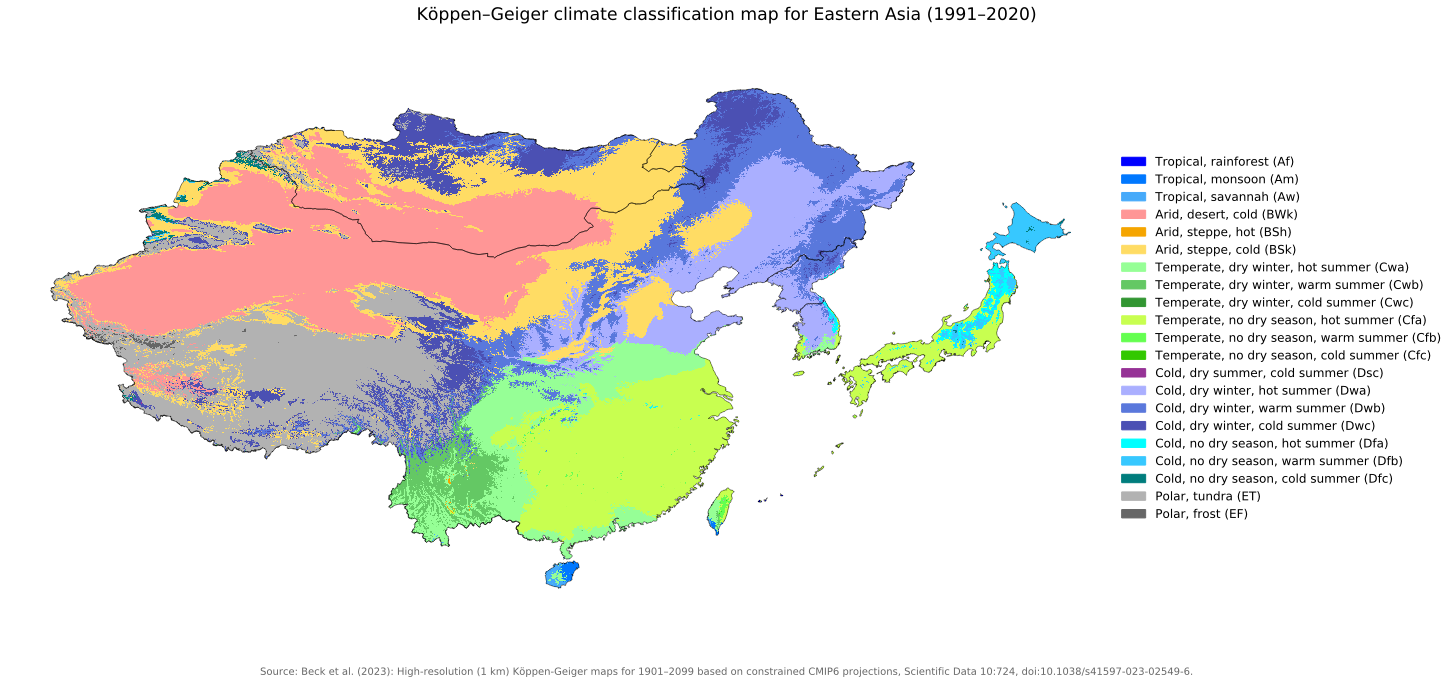東アジアの資源分布|一番の資源国はやはり…?
東アジアといえば工業や輸出で有名な国が多いですが、そもそも「資源」ってどのくらいあるの?って気になりませんか?
結論を先にいえば、資源の豊富さで見ると中国が圧倒的で、エネルギー・鉱物・レアアースのどれをとっても群を抜いているんです。他の国はどうなのかも含めて、東アジアの資源分布をチェックしてみましょう!
|
|
|
|
|
|
中国は圧倒的な資源大国
中国は面積も広く地形も多様なので、自然資源の宝庫と言われています。数の多さだけじゃなく、種類の多さもスゴい。
石炭・鉄鉱石などの鉱物資源
中国は世界有数の石炭埋蔵国で、国内の電力供給の主役にもなっています。内モンゴルや山西省が主な産地。また鉄鉱石や銅、アルミニウムなどの鉱物も多く採れます。
レアアースの世界最大産出国
スマートフォンやEVに欠かせないレアアース(希土類)は、世界の7割以上を中国が供給。南部の江西省や内モンゴルに大規模な鉱床が集中しています。
石油と天然ガスもそこそこ
タリム盆地や渤海湾などから石油・天然ガスも採れますが、輸入依存が高まっていて、戦略備蓄や海外依存リスクが課題になっています。
|
|
|
モンゴルは資源依存型の経済構造
人口は少ないですが、地中にはたくさんのお宝が眠っているのがモンゴル。経済もそれに大きく頼っています。
銅と金の大鉱山
南ゴビにあるオユ・トルゴイ鉱山は、世界最大級の銅・金鉱山。ここからの輸出が国家収入の柱になっています。
石炭とウランも豊富
中国向けに石炭を輸出するルートが整備されており、エネルギー資源国としての立場も強化中。また、ウランも埋蔵されていて、将来の戦略資源として注目されています。
|
|
|
北朝鮮にも実は資源がある?
あまり知られていませんが、北朝鮮にも天然資源はそこそこあります。ただし、制裁や体制の問題で十分に活用できていないのが現状。
鉄鉱石と石炭が中心
特に咸鏡道(ハムギョンド)あたりでは鉄鉱石が採れ、国内産業や中国への輸出に利用されています。石炭も主力ですが、インフラの未整備で輸出力は限定的。
レアメタルの可能性も
タングステンやグラファイトなど、戦略的な鉱物資源も一部にはありますが、国際的な技術・資本が入らないため、有効活用が難しい状況です。
|
|
|
日本・韓国・台湾は資源に乏しい?
これらの国は工業国として有名ですが、資源面ではどうしても不利な立場。だからこそ工夫と技術で勝負しているんです。
日本:わずかな鉱山と海洋資源
かつては銅や金の鉱山もありましたが、現在はほぼ枯渇。海底資源(メタンハイドレートやマンガン団塊)への期待が高まっています。
韓国:鉱物資源に乏しい
韓国はほとんどの鉱物資源を輸入に頼っており、加工技術と精密産業で付加価値を生むスタイル。
台湾:戦略備蓄と省資源化が鍵
資源はほとんどありませんが、IT産業や製造業が強いため、輸入資源の効率利用と備蓄政策に力を入れています。
|
|
|
資源分布がもたらす国際関係への影響
資源の有無は、その国の経済だけじゃなく、外交や安全保障にも深く関係してくるんです。
中国とレアアース外交
中国は過去に、レアアース輸出を外交カードとして使ったことがあります。これは世界中に「資源の偏在リスク」を印象づける事件でした。
資源の争奪と海洋権益
東シナ海や南シナ海などでは、海底資源をめぐる領有権争いが続いています。石油や天然ガスの埋蔵が見込まれるからこそ、各国の主張も強まるわけですね。
再生可能エネルギーと脱資源化の動き
資源のない国ほど再エネに力を入れていて、日本や韓国、台湾では風力・太陽光・水素技術の開発が進んでいます。これは資源依存からの脱却という戦略でもあります。
東アジアで最も資源に恵まれているのは、やっぱり中国です。とくにレアアースの世界的シェアは圧倒的で、これが国際的な影響力にもつながっています。一方で、資源が乏しい日本や韓国、台湾は、逆に技術や省エネで勝負しているのが面白いところ。資源の有無がその国の戦略や国際関係まで左右するって、ちょっと不思議で、でも納得の話ですよね。
|
|
|