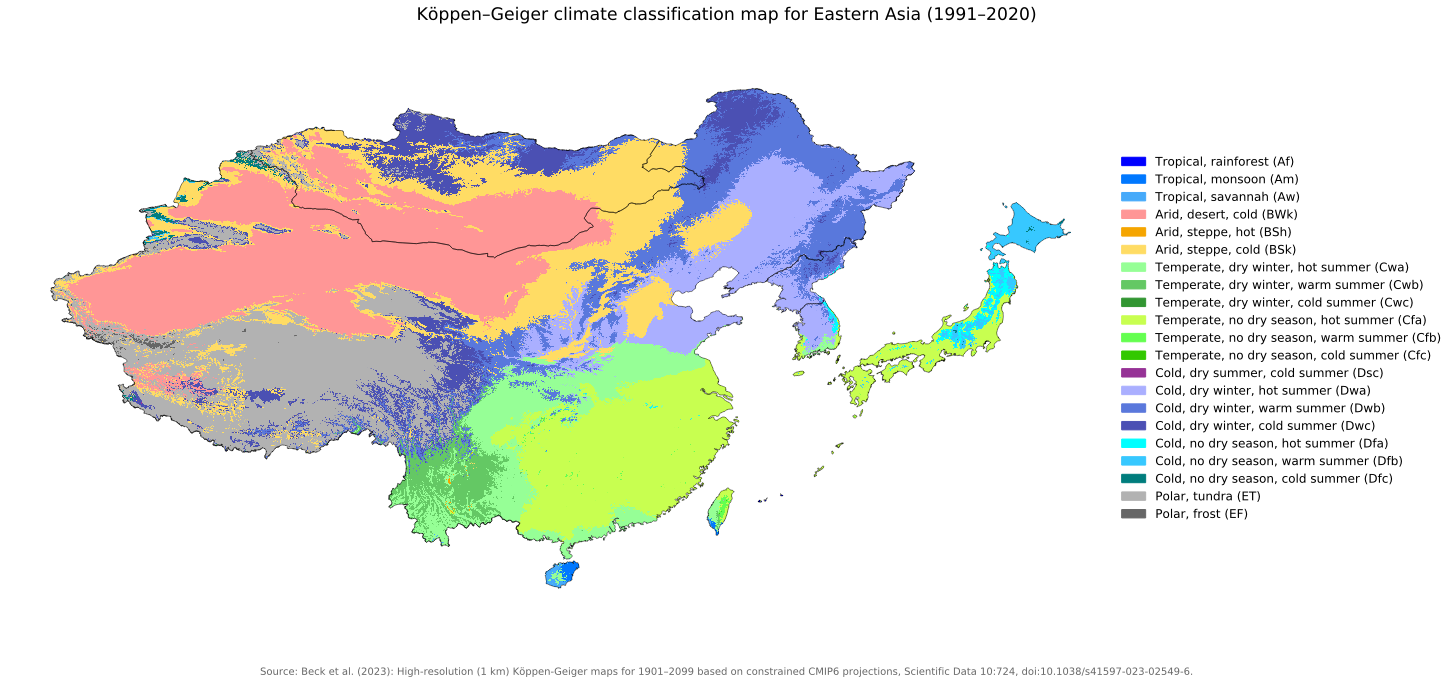東アジアの人種|モンゴロイドが多い理由は?
東アジアの国々を旅してみると、「なんとなく顔立ちが似てる?」って感じること、ありませんか?もちろん人それぞれですが、共通する特徴があるのも事実。つまるところ、東アジアには「モンゴロイド(アジア系人種)」が多いのは、氷河期の環境適応や長い移動の歴史によって、似たような身体的特徴が進化的に定着したからなんです。今回は、そんな「人種」のちょっと面白い雑学を交えて解説していきます!
|
|
|
|
|
|
モンゴロイドってそもそも何?
「モンゴロイド」という言葉、最近はあまり使われなくなってきましたが、かつては世界の人種を大きく3つに分ける分類のひとつでした。
3大人種のひとつ
19世紀~20世紀にかけて、世界の人種は以下のように分類されていました:
- コーカソイド(ヨーロッパ系)
- ネグロイド(アフリカ系)
- モンゴロイド(アジア系)
モンゴロイドは東アジア、東南アジア、北アジア、アメリカ先住民などに広がるグループで、黄色人種とも呼ばれていました。
身体的特徴の傾向
あくまで傾向ですが、以下のような特徴が見られることが多いです:
- 地毛が黒くて直毛
- 肌は黄色がかった褐色
- 頬骨が張っている
- 目元に蒙古ひだがある
- 体毛が薄め
これらの特徴は、寒冷地や強い風、紫外線などの環境に適応した結果と考えられています。
|
|
|
東アジアにモンゴロイドが多い理由
では、なぜ東アジアにこの「モンゴロイド系」がこんなに広がっているのでしょうか?その理由は大きく3つあります。
寒冷地への進化的適応
氷河期の時代、東アジアやシベリアに住んでいた人々は、寒さと乾燥に耐える必要がありました。蒙古ひだや平たい顔立ちは、風や寒さから目や顔を守るために進化した形とも言われています。
拡散ルートの集中
人類はアフリカから出てユーラシア大陸へと広がりましたが、その途中で中東~中央アジア~東アジアというルートが最も安定していたため、多くの人がこの地域に定着しました。結果的にモンゴロイド系の祖先がこの地で増えたわけです。
アメリカ先住民との共通祖先
東アジアにルーツを持つ人々の一部は、ベーリング海峡を渡ってアメリカ大陸へ移動しました。アメリカ先住民がモンゴロイドに似た特徴を持つのは、この移動の名残です。
|
|
|
国別で見る人種のバリエーション
一括りに「モンゴロイド」と言っても、国や地域によっていろんなバリエーションがあるんです。それぞれの特色もちょっと見てみましょう。
中国:多民族国家の顔の多様性
漢民族が多数派ですが、チベット族・ウイグル族・モンゴル族・朝鮮族など、顔立ちや体格にもバリエーションがあります。
モンゴル:遊牧民の頑丈さ
高地での生活、寒さと強風の中で鍛えられたがっしり体型が特徴的。顔立ちも広く、頬骨が高くて彫りが深めな人も多いです。
日本・韓国:古代の混血の影響
日本列島には縄文人と弥生人という二系統の祖先がいて、南方系と北方系の混血が進んだ結果、独自のバランスのとれた顔立ちが形成されました。韓国も、中国東北部との交流を通じて似たような構造があります。
|
|
|
現代ではどう扱われているの?
「モンゴロイド」という言葉自体、いまではあまり使われなくなってきていて、その背景には歴史的な配慮や新しい人類学の考え方があります。
人種よりも「遺伝子多様性」へ
近年の研究では、人種という概念は生物学的にあいまいとされ、代わりに遺伝子の地域的多様性という見方が主流になってきています。
差別的ニュアンスの排除
かつて「モンゴロイド」という言葉が差別的に使われた歴史もあるため、公的な場ではアジア系(Asian)や東アジア系など、より中立的な表現が使われるようになっています。
文化的アイデンティティの強調
現代では「人種」ではなく、文化圏・価値観・言語といったアイデンティティを軸に、自分たちのルーツを語る流れが強くなっています。
東アジアにモンゴロイドが多いのは、進化的な環境適応と移動の歴史が重なった結果なんです。そして今では、その共通性よりも「文化や価値観の多様さ」が重視される時代。人種っていう枠組みの裏にも、長い歴史と進化のドラマがあるって思うと、なんだかワクワクしませんか?
|
|
|