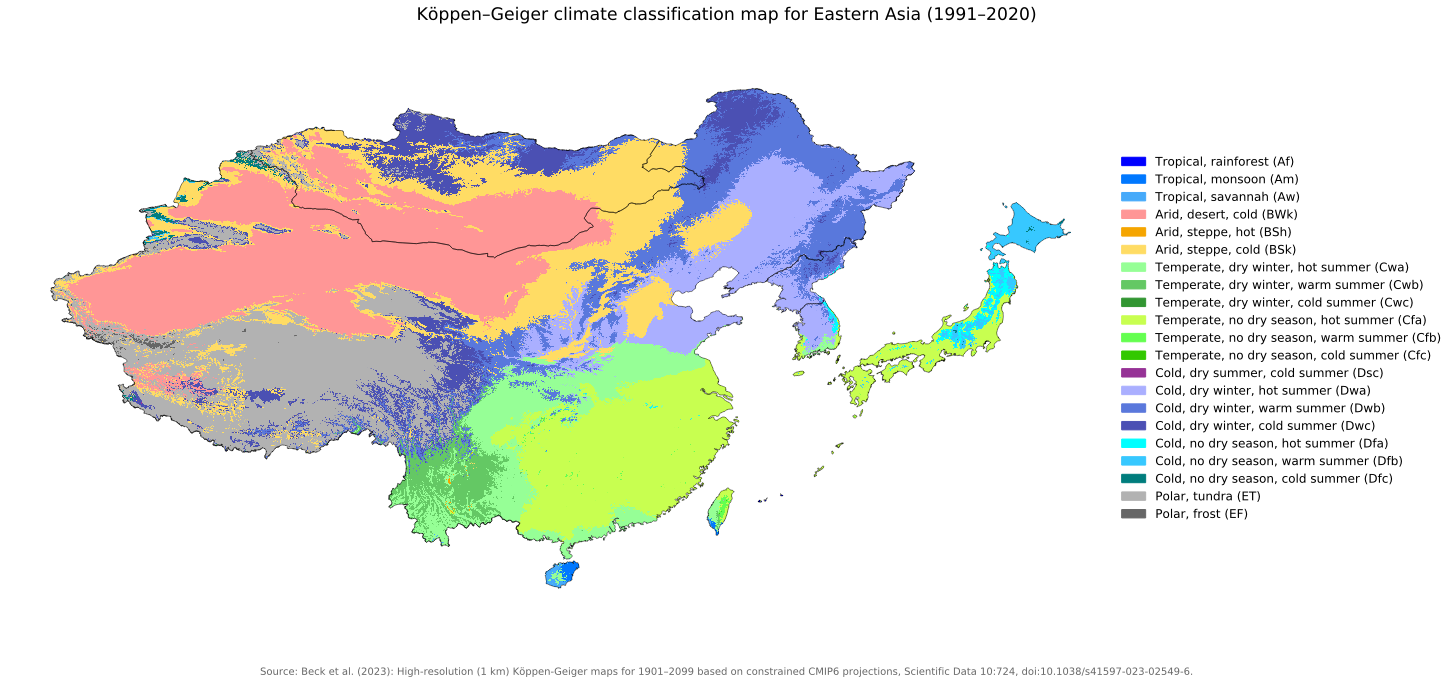東アジアの思想史|各国は「何主義」を選択したのか…
東アジアの歴史をひもとくと、政治や社会の土台にはいつも「思想」がありました。とくに国家の運営や教育、価値観において、それぞれの国が選び取ってきた「主義」はかなり違います。どういうことかというと、東アジアでは中国・朝鮮・日本などが、それぞれの歴史や状況に応じて、儒教・仏教・法家・朱子学などの思想を使い分けてきたんです。今回はそんな東アジアの思想の流れと、各国が選んだ「主義」について整理してみましょう。
|
|
|
|
|
|
中国の思想:儒教と法家のせめぎ合い
中国は東アジア思想の震源地とも言える国で、さまざまな哲学体系が古代から生まれてきました。その中でも二大巨頭といえば、やっぱり儒教と法家。
儒教:道徳と秩序の思想
孔子が始めた儒教は「仁・義・礼・智・信」を重んじる、人間関係と道徳を中心に据えた考え方。前漢以降、国家の公式イデオロギーとして採用され、皇帝から庶民まで価値観の基本となりました。
法家:法律と権力による統治
秦の始皇帝が採用した法家は、ルールと罰則で民を統治するリアリズム志向の思想。性悪説をベースに、厳罰主義で秩序を保とうとしたのが特徴です。
漢から宋にかけての「朱子学」
儒教が時代とともに進化し、宋代には朱子学が登場。これは道徳の内面化を重視する新しい儒教で、後の朝鮮や日本にも強く影響を与えます。
|
|
|
朝鮮の思想:徹底した朱子学国家
李氏朝鮮は中国の影響を受けながらも、思想面では独自の発展を遂げました。選び取ったのは、道徳規範を極限まで突き詰めた「朱子学」でした。
朱子学の国教化
朝鮮王朝は朱子学を国家の基礎思想として取り入れ、学校教育や官僚登用(科挙)にも取り入れました。仏教を排除してまで朱子学を推進したのは、王朝の正統性と秩序を保つためです。
性理学と道徳主義
朱子学の影響で「礼節」「家族制度」「祖先崇拝」などが極端なまでに重視されました。性理学という呼ばれ方もされ、庶民の暮らしにも深く根付いていきました。
仏教と民間信仰の共存
表向きは朱子学一色でも、山間部では仏教が静かに生き残り、シャーマニズム的な民間信仰と融合する形で庶民の間では息づいていました。
|
|
|
日本の思想:取り入れてアレンジする国
日本は思想に対して「選んで取り入れ、うまく使い分ける」スタンスが目立つ国。儒教も仏教も神道も、混ぜながら使ってきたのが日本らしいところです。
仏教と神道の習合
古代から伝来した仏教は、日本古来の神道と融合し、「神仏習合」という独自のスタイルに。宗教というより「生活文化」に近い形で根づきました。
朱子学の導入と武士道化
江戸時代には朱子学が幕府の公認学問となり、士農工商の秩序や忠義の精神に活かされました。やがて「儒教+武士道」のような独自の思想が育まれます。
陽明学や国学とのせめぎ合い
朱子学に反発して、実践を重んじる陽明学や、日本の古典を見直す国学も登場。それぞれが幕末の志士や明治の思想家たちに影響を与えていきます。
|
|
|
現代に受け継がれる思想のかたち
思想って古臭いものと思われがちだけど、今も社会の中にしっかり生きているんです。それぞれの国にどんな形で残っているのかを見てみましょう。
中国:儒教回帰と国家主義
経済成長とともに儒教が「社会の安定」や「家族の絆」の源として再評価される動きがあります。また、統治思想として国家主義との融合も進んでいます。
韓国:儒教的家族観と個人主義の衝突
現代韓国では、家父長的価値観が残る一方で、若者を中心に個人主義や自由主義への転換が進み、価値観の転換期を迎えています。
日本:多元的な思想の共存
日本では宗教や思想を明確に一つに絞らない傾向があり、神道・仏教・儒教・西洋哲学が生活の中で自然に混在しています。「なんとなく尊敬」「なんとなく節制」という感覚的な受容も日本らしさです。
東アジアの思想史は、国ごとにまったく違う選択と歩み方があったんです。中国は儒教と法家の使い分け、朝鮮は徹底した朱子学、日本はアレンジ文化。そしてその思想は、今の社会や価値観にもつながっているからこそ、知っておくと世界の見え方がぐっと広がるかもしれませんよ。
|
|
|