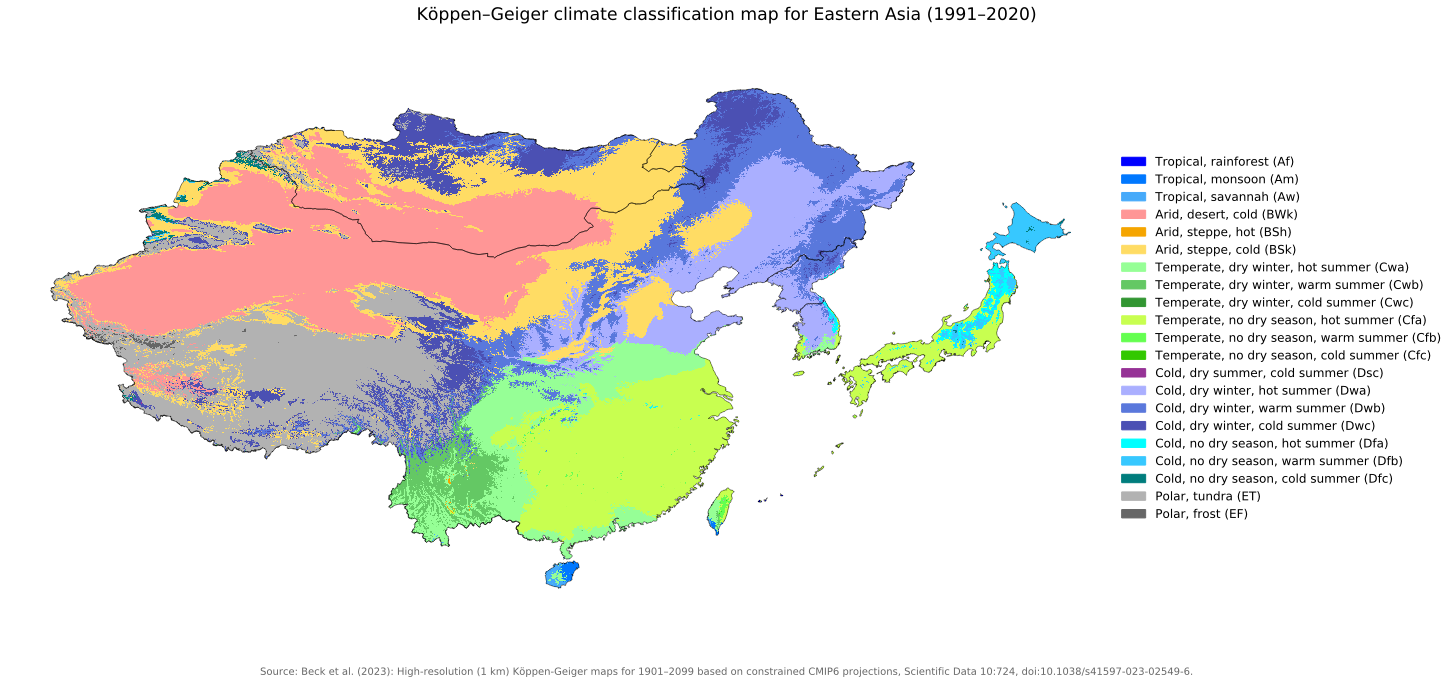東アジアの貨幣史|古代~現代にかけての通貨変遷とは?
お金って、あまりに身近すぎて気にしないけど、実はその歴史をたどると社会の姿や価値観の変化が見えてきたりするんです。どういうことかというと、東アジアの貨幣は「政治権力の安定」と「交易ネットワークの広がり」によって形を変えてきたんです。今回は古代から現代までの流れをざっくり見ながら、それぞれの時代の通貨がどんな背景で使われていたのかを解説していきますね!
|
|
|
|
|
|
古代の貨幣|貝殻から金属へ
最初に「お金」が登場したのは、まだ国家らしい国家ができる前。東アジアの貨幣史は、物々交換から始まり、やがて象徴的な「貨幣」へと変化していきます。
中国の貝貨と刀銭
中国の最初期のお金とされるのが貝貨。実際の貝殻が珍重され、儀式や取引で使われていました。その後、金属を加工した刀銭(ナイフの形)や布銭(クワの形)といった地域通貨が登場します。お金の形にも土地の文化が反映されてるのが面白いですね。
日本の和同開珎
日本では、708年に発行された和同開珎(わどうかいちん)が最初の本格的貨幣とされています。ただし、当時は米や布がまだ主流だったため、貨幣はあくまで一部の流通手段に過ぎませんでした。
|
|
|
中世の貨幣|中国の覇権と銅銭の海
東アジアの中世では、中国の存在感が圧倒的。通貨の流通も、ほぼ中国中心に回っていたといっても過言じゃありません。
宋の銅銭がアジアに広がる
宋(そう)王朝の時代、中国では商業が盛んになり、銅銭(開元通宝など)が大量に鋳造されました。これが日本や朝鮮、東南アジアにまで流れ込み、いわば「東アジア共通通貨」みたいな働きをしていたんです。
日本での輸入銭使用
日本では室町時代まで銅銭の輸入が盛んで、「永楽通宝」などの中国銭がそのまま使われていました。まだ日本国内での鋳造は少なかったため、対中国貿易は「貨幣の輸入」でもあったんですね。
|
|
|
近世の貨幣|国ごとの独自通貨へ
時代が進むにつれ、各国が安定した政府を持つようになると、自国通貨を発行する動きが広がっていきます。
日本の金銀銭三貨制度
江戸時代の三貨制度では、「金(主に江戸)・銀(主に大坂)・銭(全国で流通)」が使い分けられ、それぞれ価値の基準も違っていました。重さや品位もバラバラだったので、計算が複雑だったという話も。
朝鮮の常平通宝
朝鮮でも17世紀以降に常平通宝などの銅銭が発行され、国内流通の安定が図られました。ただし、物価の変動や貨幣の偽造などの課題も多かったようです。
|
|
|
近代の貨幣|国家制度と紙幣の登場
明治維新や清の崩壊など、19世紀は東アジア各国が激動の時代。貨幣制度もそれに合わせて大きく近代化されていきました。
日本の円の誕生
1871年に新貨条例が発布され、日本円が誕生。1円=100銭=1,000厘という十進法が導入されました。西洋にならった紙幣や造幣技術の導入で、ようやく現代的な通貨制度がスタートします。
清の銀本位と中華民国の紙幣
一方、中国では清の時代に銀本位制が使われており、銀の秤量が基本でした。中華民国以降は法幣や銀元など複数の紙幣が流通しましたが、戦争や政争でしばしば混乱が生じました。
|
|
|
現代の貨幣|電子化と信用経済の時代へ
21世紀の今、貨幣はどんどん「形」を失っています。通貨の役割も、単なるモノのやり取りから、信用の担保へと変化してきています。
デジタル人民元とキャッシュレス中国
中国では世界に先駆けてデジタル人民元の実証実験が行われ、WeChat Payやアリペイなどのスマホ決済が都市部で日常化。もはや「現金を見ない生活」が珍しくない状況です。
日韓台のキャッシュレス化
日本はキャッシュ文化が根強いとはいえ、最近ではPayPayや交通系ICカードの利用が拡大中。韓国はクレジットカードの普及率が高く、台湾もQRコード決済が進んでいます。
通貨って、「ただの買い物の道具」じゃなくて、その国の歴史や経済のカタチを映す鏡なんですよね。東アジアの貨幣も、王朝の興亡、交易の広がり、近代国家の誕生、そしてテクノロジーの進化とともに形を変えてきました。財布の中の硬貨やスマホの決済アプリ、その奥にある「通貨の物語」に、ちょっとだけ思いを巡らせてみてはいかがでしょうか?
|
|
|