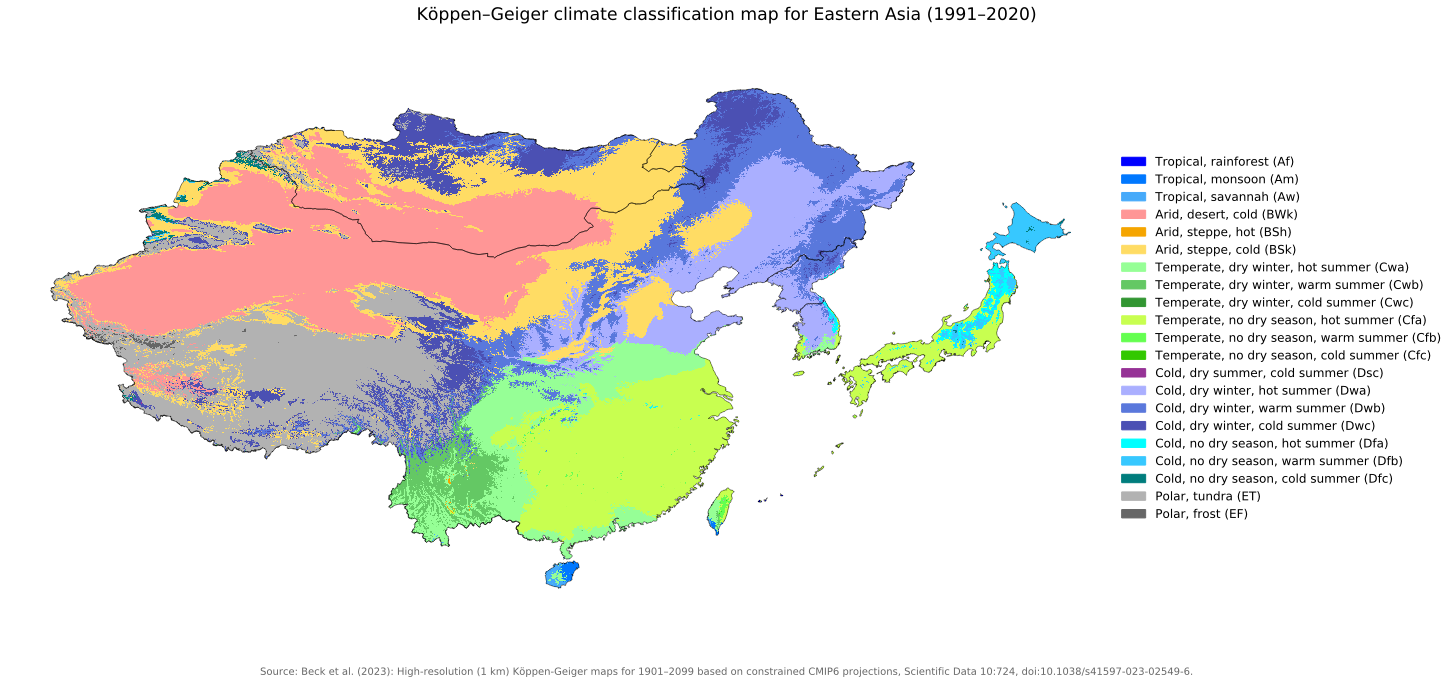東アジアの内陸国|内陸ゆえのメリット・デメリットとは?
東アジアと聞くと、海に囲まれた国のイメージが強いですが、実は海にまったく面していない内陸国もあるんです。たとえばモンゴルがその代表例ですね。
そして内陸国は、「海がない」という地理的な特徴が、経済や外交、安全保障において独特なメリットとデメリットをもたらしているって知ってましたか?今回は東アジアにおける内陸国と、その特性について詳しく見ていきましょう。
|
|
|
|
|
|
東アジアの内陸国ってどこ?
まずは「内陸国」と呼ばれる国が、東アジアではどこにあるのか確認しておきましょう。基本的にはモンゴルが唯一の内陸国とされますが、地域によっては一部の自治区もそれに近い条件を持っています。
- モンゴル
- 中国内陸部(新疆ウイグル自治区、チベット自治区など)
- 内モンゴル自治区(中国)
- 黄土高原地帯
- タリム盆地
- オルドス高原
こうした地域では、海からのアクセスがないぶん、物流・気候・外交に特有の影響を受けます。
|
|
|
内陸国のメリットとは?
「海がない=不利」と思われがちですが、実は地政学的に有利な側面もいくつかあるんです。
海洋侵略のリスクが少ない
海に面していないので、海軍による攻撃を受けることがまずありません。国境線がすべて陸地なので、防衛戦略も陸上に集中できます。
文化の交流拠点になりやすい
歴史的には、交易路の交差点として栄えた都市が多く、モンゴル帝国時代のように広範囲の文明が交わる地になったこともあります。
自給自足型の農牧業が発展しやすい
外部からの資源供給に頼らずに内需で回す産業が育ちやすいのも特徴です。とくに遊牧民の伝統文化と経済が根強く残っているのは内陸特有の風景ですね。
|
|
|
内陸国のデメリットは?
とはいえ、現代においては「海がない」という条件は、いくつかの経済的・外交的なハンデを生むこともあります。
輸出入コストが高い
海上貿易が使えない分、陸路か空路に頼るしかなく、コストがかさみやすいです。とくに重いもの・大量の物資を扱う産業にとっては大きな障壁になります。
国際市場とのアクセスが不利
港がないので、世界経済との距離感が生まれやすく、グローバルサプライチェーンに乗りにくいことも。外資導入や先端技術の流入が遅れがちです。
近隣国への依存度が高くなる
輸送や通信のインフラが周辺国経由に限られるため、政治的に安定していないとすぐに孤立するリスクも。モンゴルは中国とロシアに挟まれており、どちらかの影響力が常に強く働きます。
|
|
|
東アジアにおけるモンゴルのケース
東アジアで唯一の内陸独立国家モンゴルは、その地理的条件とどう向き合ってきたのでしょうか?
地政学的バランス外交
中国とロシアという大国に挟まれているため、「第三の隣国外交」(日本やアメリカ、EUなどとの関係強化)というユニークな外交戦略を展開しています。
鉱山資源を生かした経済構造
銅・金・石炭などの鉱物資源を輸出の柱とし、内陸でも収益を上げられるモデルを構築。ただし、資源価格の変動に大きく左右されやすいのが課題です。
物流整備への国家的努力
港が使えない分、鉄道や道路インフラの整備が重要視されており、中国との鉄道接続強化などが進められています。
東アジアの内陸国であるモンゴルや周辺地域は、「海がない」というだけで損をしてるように見えるかもしれませんが、そのぶん独自の戦略や文化が発展しているんです。もちろん不利な点もあるけれど、それを乗り越える工夫や地理の活かし方が、じつはとっても興味深いんですよ。
|
|
|