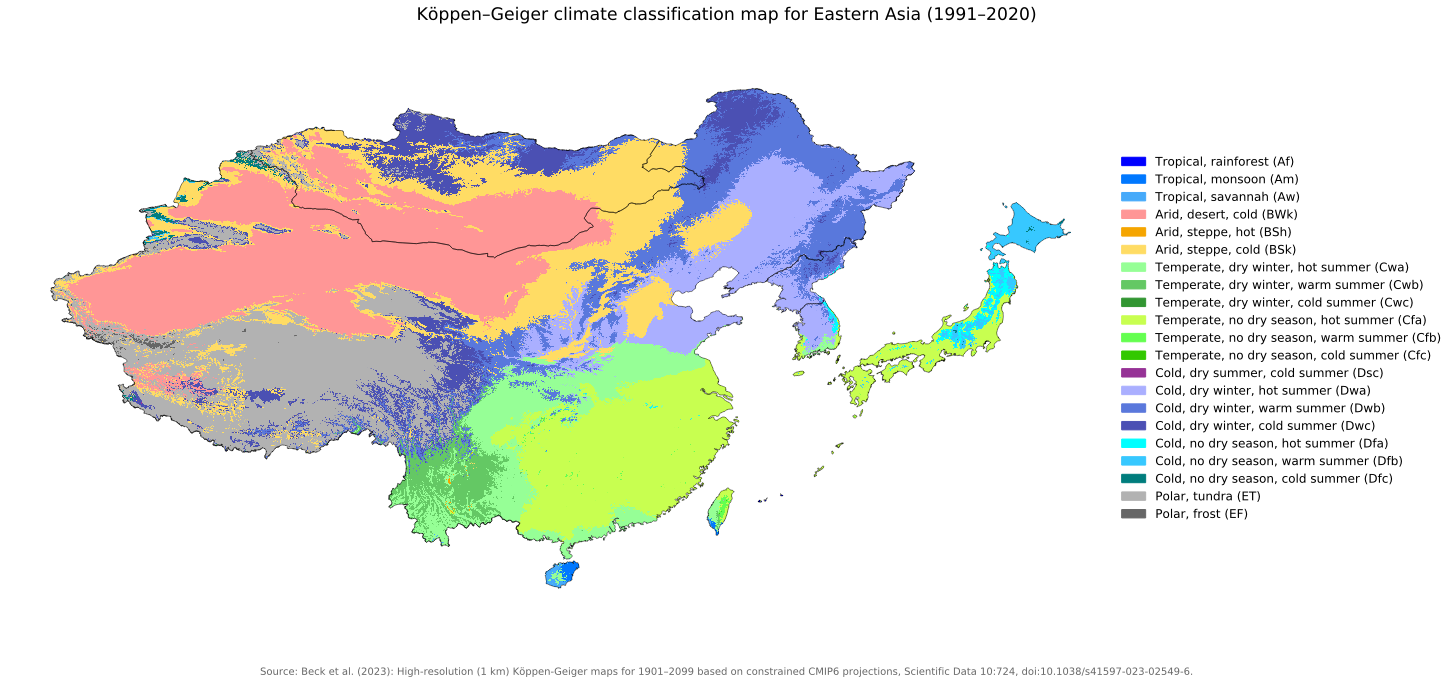東アジアの植民地時代|植民地化はいつから?抵抗運動の歴史を知る
東アジアの近代史を語るうえで避けて通れないのが「植民地化」の時代です。どういうことかというと、19世紀後半から20世紀にかけて東アジアの国々は欧米列強や日本によって植民地化され、そこには激しい抵抗と独立のための闘いの歴史があったということなんです。今回は、東アジア各国がいつから植民地支配を受け、どんな形で抵抗したのかを見ていきましょう。
|
|
|
|
|
|
東アジアの植民地化はいつ始まった?
まずは、東アジアのどの国がいつから植民地となったのか、ざっくりと時系列で押さえておきましょう。
中国:アヘン戦争からの半植民地化
中国は完全な植民地にはされませんでしたが、1839年のアヘン戦争以降、列強による半植民地化が進みました。香港はイギリスに割譲され、各地に租界(外国人居留地)が設置されます。
朝鮮:日本の保護国化から併合へ
朝鮮は19世紀末、日本と清の争いの中で独立を保っていましたが、日清戦争後に日本の影響下へ。1905年の保護条約、そして1910年には日本による併合が行われ、35年にわたる植民地支配を受けました。
台湾:日清戦争の結果、日本の領土に
台湾は1895年の日清戦争の結果、日本に割譲されました。以後、1945年までの50年間、日本の植民地として統治されました。
モンゴル:中国とソ連のはざまで
モンゴルは清の支配下にありましたが、1911年の辛亥革命後に独立を宣言。その後はソ連の影響下に置かれ、形式的には独立国でも衛星国として支配を受けました。
|
|
|
各国で起きた抵抗運動の歴史
植民地支配に対して、東アジアの人々はじっとしていたわけではありません。さまざまな形で抵抗運動が展開されました。
中国:義和団事件と辛亥革命
1900年には外国勢力を排除しようとする義和団事件が勃発。さらに1911年には孫文らによる辛亥革命が起き、清が倒れて中華民国が成立します。これは対外支配への象徴的な転換点でした。
朝鮮:三・一独立運動と臨時政府
1919年、パリ講和会議に合わせて三・一独立運動が全国的に発生。日本の弾圧を受けながらも、韓国臨時政府(大韓民国臨時政府)が中国・上海で設立され、独立運動が海外にも広がりました。
台湾:武力・文化による二重の抵抗
台湾でも1895年の「台湾民主国」による短期間の抵抗や、1930年の霧社事件などの武力闘争が行われました。また、日本語教育に対抗して台湾語・中国語文化を守る動きも活発でした。
モンゴル:革命と宗教的抵抗
モンゴルではソ連型の共産革命が行われた一方で、仏教僧院の破壊に対する宗教的な抵抗も起きました。民族アイデンティティの保持が大きなテーマでした。
|
|
|
植民地支配の特徴と影響
東アジアにおける植民地支配には、それぞれに共通する特徴もあれば、国ごとに違った側面もあります。
経済の収奪とインフラ整備
植民地経済は支配国の利益中心に動きました。鉱山・農園が作られ、鉄道や港湾が整備されましたが、その恩恵は現地住民にはあまり届きませんでした。
言語・文化の強制
日本は台湾や朝鮮で日本語教育を徹底し、皇民化を進めました。中国では列強の租界ごとに欧米の文化・制度が流入し、伝統的な価値観が揺らぎました。
民族意識とナショナリズムの芽生え
抑圧の中から「自分たちは何者か?」を問い直す動きが生まれ、民族主義が育ちました。この意識が、後の独立運動や国家建設につながっていきます。
|
|
|
戦後の独立・解放とその後の課題
第二次世界大戦の終結とともに、多くの植民地は解放されましたが、その後も様々な課題が残されました。
台湾と中国の統一問題
戦後、日本の降伏により台湾は中国(中華民国)に返還されましたが、その後の国共内戦によって二つの中国問題が生まれ、今日まで続いています。
朝鮮半島の分断
日本からの解放後、南北でアメリカとソ連の影響を受けた分断国家が誕生し、朝鮮戦争を経て現在も統一は実現していません。
中国の内戦と共産化
中華民国と中国共産党の争いが激化し、1949年に中華人民共和国が成立。共産党政権による新たな統治が始まりました。
東アジアの植民地時代は、単に「支配された」というだけではなく、その中でいかに抵抗し、自分たちの存在を守ろうとしたかという人々のドラマでもありました。支配の痛みを経て生まれたナショナリズムや独立の動きは、今の東アジアの国家のあり方や国際関係にも深く影響しているんです。だからこそ、この時代を知ることは、過去だけでなく今と未来を考えるヒントにもなるんじゃないでしょうか。
|
|
|